インタビュー
4月4日養子の日 すべては赤ちゃんの命を救うために 産婦人科医・菊田昇医師の妻・菊田静江さんインタビュー
<産婦人科医・菊田昇医師の妻・菊田静江さんインタビュー>
すべては赤ちゃんの命を救うために
菊田昇医師の闘いが残してくれたものとは

特別養子縁組は、1987年の民法改正時に導入された制度です。この制度ができた背景には、宮城県石巻市の産婦人科医、故・菊田昇医師が深く関わっていたといわれています。あれから約30年が経ち、法律面では児童福祉法の改正、養子縁組あっせん法の成立(2016年)という大きな進歩がありました。とはいえ、まだ多くの課題はあります。私たちは引き続き、「子どもの最善の利益を保証するためにどうすればよいか」を考え、より良い実践につなげていかなくてはなりません。こうした思いを胸に、ハッピーゆりかごプロジェクトでは、現在も宮城県にお住いの菊田昇先生の妻、菊田静江さんを訪ね、当時の菊田先生のこと、そしてこれからの特別養子縁組制度についての思いをお聞きしました。
◇菊田昇医師について
1973年4月17日と18日、石巻の新聞2誌に小さな広告が掲載されました。
「急告 生まれたばかりの男の赤ちゃんをわが子として育てる方を求む」。
これが、全国で大論争となった、いわゆる「赤ちゃんあっせん事件」の発端です。菊田医師は、中絶を懇願してくる女性を「出産したことを戸籍に残さないから」と説得し、産まれた子を育ての親となる信頼できる夫婦に託していました。戸籍法、医師法に抵触する行為だとは知りつつも、赤ちゃんの命を守るために行った行動は、世論を動かし、1987年の特別養子縁組制度の成立を後押ししました。
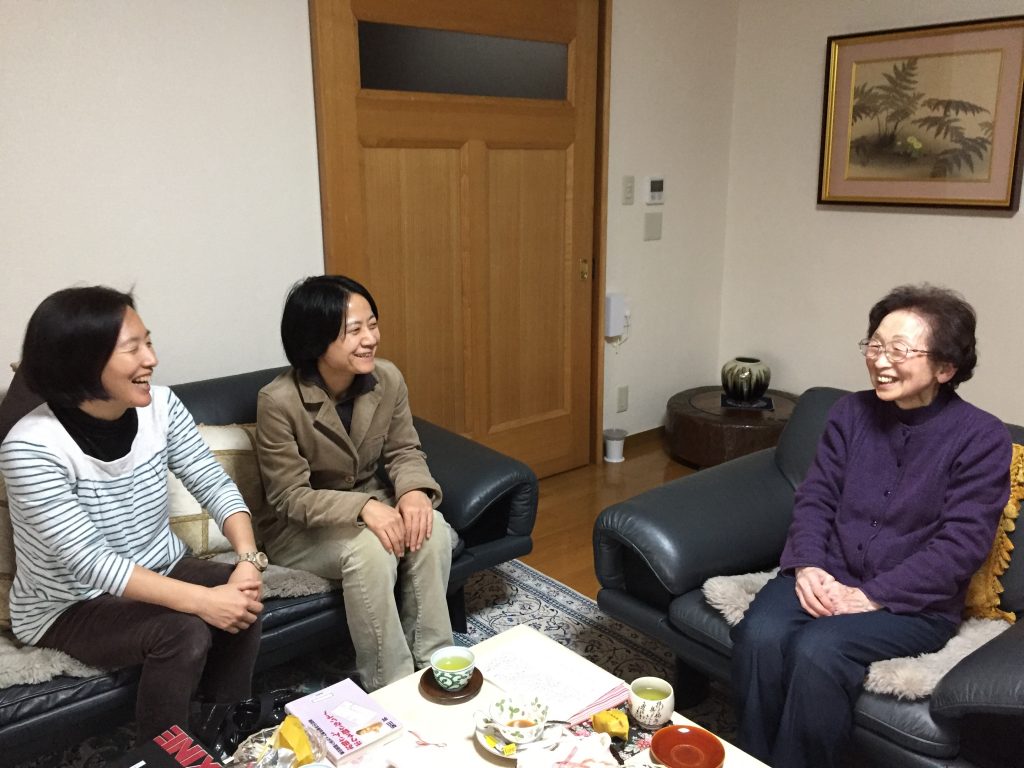
赤ちゃんの命を葬ることは忍びなかった
――菊田先生は、地元紙の3行広告を通して養子縁組のことを公にされて、この問題を世に問われました。当時は静江さんに何かご相談はありましたか?
菊田静江さん(以下同) 主人はこうと決めたら一人で突き進んでいく性格でしたし、私は診療関係のことは基本的にはノータッチでした。養子縁組のことも秘密裏にしなくてはならないので、実は公になるまで詳しいことは聞いていませんでした。ですから、新聞に出たときは私もとても驚きました。
――当時は妊娠7カ月(28週未満)でも合法的に手術ができたそうですね。
主人は中絶の依頼が多いことに心を痛めておりました。当時の石巻は賑やかな港町で開放的だった半面、未婚のお母さんに対しての世間の目は厳しいものがありましたから、妊娠をして「育てられない」「周囲に知られたら生きていけない」と、駆け込んでくる女性は多く、中には妊娠7カ月を超えているような方もいました。その頃の法律では妊娠7カ月でも中絶ができることになっていました。でも赤ちゃんはもうお腹の外に出ても十分に生きていけるほど育っています。当時の産婦人科医の専門誌にもそのことに関する論文が載っており、主人はその原稿に目を通して、考えを巡らせていた様子でした。
一方で、産婦人科には「なかなか子どもができない」と不妊治療のご相談でいらっしゃるご夫婦もいましたので、そうした方々を結びつけたのだと思います。
間違ったことはしていない、だから支えられた
――公になってからは、賛否両論があったと思います。どのようなお気持ちで受け止められていましたか?
「これは大変なことになった」と思いました。それでも、主人が決断したことですし、養子縁組につなげたということは、それだけ赤ちゃんの命が救われたのです。何も間違ったことはしていない、という確信がありました。だからこそ、私は支え続けることができました。また、主人の友人たちはみな賛同してくださいましたし、遠い親戚などの身内も好意的に受け止めて、協力してくださいました。
主人は産んだ女性の戸籍に残らないで養子縁組できる「実子特例法」の制定を訴え続けていました。有志の「実子特例法推進委員会」が署名運動をしてくれたり、養子縁組の活動を行っていらっしゃる団体から講演に呼ばれたりもしました。
しかし、当時の医師会からは、非合法だからというだけでなく、中絶の問題を明るみに出したことへの反発もありました。「自分だけが赤ちゃんを救おうとしたと思っている」と非難する方もいたようです。主人は、以前から医師会の先生方には中絶をしなくてすむ方法を相談したこともあったようですが、あまりよい反応がなかったため、結局は自分だけで行動を起こしたのだと思います。
――菊田先生が願っていた実子特例法とは異なる点もありますが、特別養子縁組制度が成立し、戸籍に「長男」、「長女」と実子と同じように記載できるようになったことは、画期的なことでした。
そのことはとても喜んでおりました。ただ、産んだ方の戸籍に残らないことがいちばん望ましいとは思っていました。
公になってからは、全国の妊娠に悩む女性からの相談が相次ぎました。玄関に赤ちゃん置き去りにしていく人も現れてしまいました。また、子どもを育てたいという方々も集まってこられましたので、面接をして、帳簿にも記録を付けて管理を始めました。医師は菊田一人、あとは7人ほどの看護師さんたち職員が一丸となって対応しておりました。養子縁組が成立したのは、主人が亡くなってからの方が多かったかもしれませんが…。

――菊田先生がお亡くなりになってからも養子縁組の仲介をなさっていたのですか?
はい、続けておりました。主人は1986年の末に大腸ガンと診断され、1991年に亡くなりました。しかしその後も、養子縁組の相談を受けることは多かったので、千葉や埼玉の産婦人科医、教会関係の有志と連携して、「赤ちゃんを救う会」で第二種社会福祉事業を申請し、17年間続けました。
メンバーは関東と東北で離れていましたが、年に1回は関東か仙台の自宅のどちらかで総会を開いていました。妊娠をして困った方の相談は産婦人科医が、お子さんが欲しいという方の相談は東京の教会関係者が一生懸命に取り組んでくれました。メンバーの親戚がアメリカで弁護士をしていた関係で、国際養子縁組が多かったです。年間に10名ほどをつないだでしょうか。私は、宮城県内の相談者の対応や、役所への届け出や帳簿の記録などの事務管理をしておりました。ときおり、子どもを養子に出した女性が、結婚のご報告や相談に来られたり、養子を迎えた家族が会いに来てくださったりもしていました。メンバーの高齢化により、2010年に正式に活動を終えました。
子どものしあわせな成長を最優先に考える
――静江さんが続けていらしたことは存じ上げませんでした。菊田先生の行動は、静江さんがクリスチャンでいらしたことの影響が大きかったのでしょうか?
私と結婚する前から教会を訪ねてキリスト教についての話を聞いたことはあったようです。ただ、開業してからは、中絶依頼に対応せざるを得なくなり、中絶を認めていないキリスト教の教義との葛藤があったようでした。子どもがキリスト教の幼稚園に通うようになると「わざわざ行く必要はない」と反対した時期もありました。しかし、自分の信念を貫いて活動をした後、ガンの手術が終わってからでしたが、洗礼を受けたいと言ってくれました。私は病床にあった主人が亡くなるまで毎夜、ベッドの横で聖書を読み続けておりました。
亡くなる4カ月前には、国際生命尊重会議・東京大会で第2回の「世界生命賞」をいただきました。第1回のオスロ大会ではマザー・テレサが受賞された賞です。ほんとうに喜んでおりました。病室でも「このような賞をいただけて、おれは幸せな男だ」と申しておりました。満足してこの世を去っていったと思います。

――医師をなさっているご長男は、熊本の「こうのとりのゆりかご」を訪ねられたそうですね。
息子たちは主人がしたことについて多くを語りませんし、活動も継いでおりませんが、何か思うところがあったのだと思います。どのように運営なさっているのか、気になっていたのでしょうか。熊本には私に何も言わず一人で出かけて行きました。お目にかかった蓮田太二先生のことを「とても、とてもお優しい先生だったよ」と感激しておりました。
――現在は法律も変わり、運用についてさまざまな検討がなされています。法律を制定している方、養子縁組の仲介をしている方々へのメッセージをいただけますか。
主人の活動が全国的に広まったとき、アメリカやフランスに留学して法律を学んでいる先生方からもお電話がありました。「日本にしかるべき法律がないのは問題ですね。私たちもしっかり勉強してきます」と言っていただきました。アメリカは当時から養子縁組に対する偏見もなく、いろんな面で進んでいました。病気があっても、重い事情を背負って産まれてきた子どもであっても躊躇なく受け入れてくださる方々もいらして、主人も私もその気高い精神に感動しておりました。
ここにきて日本の法律も整備されているということですから、さらに広く周知されれば、たくさんの困っている人を助けることができるのではないでしょうか。日本の現状にがっかりしたこともありましたが、時代は変わってきているのですね。
主人は「赤ちゃんの命を救うために、一歩だけでも進めたい」と取り組んでいました。受け継いでくださる方がいらっしゃることを心からうれしく思っています。
特別養子縁組は、親になる方々の考え方をきちんと確認しておくことが何より大切だと思います。「将来、親の面倒をみてもらう」「病気がある子は育てられない」というような考えではなく、子どものためを考えているかどうかです。
親になる方はもちろん、特別養子縁組に関わる方々も、「子どものしあわせな成長を最優先に考える」ということを、どうぞこれからも大切にしていってください。
(聞き手・高橋恵里子 赤尾さく美 構成:林口ユキ)
私たちは、社会と子どもたちの間の絆を築く。
すべての子どもたちは、
“家庭”の愛情に触れ、健やかに育ってほしい。
それが、日本財団 子どもたちに家庭を
プロジェクトの想いです。



